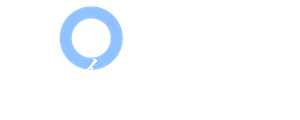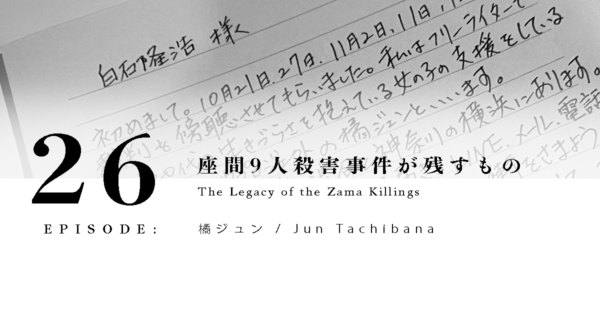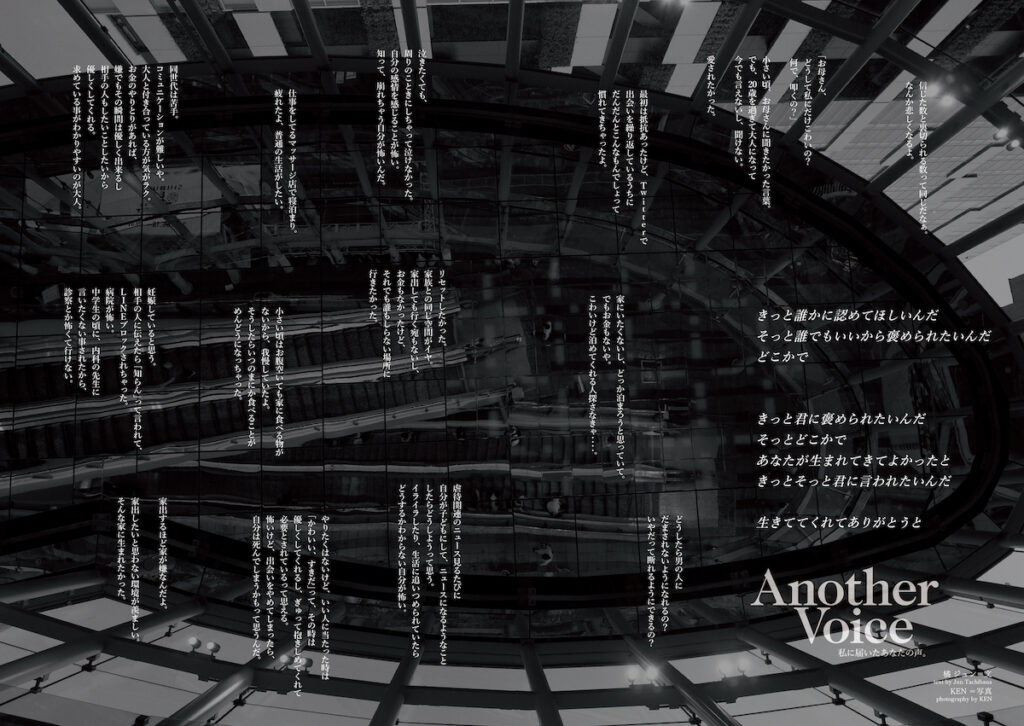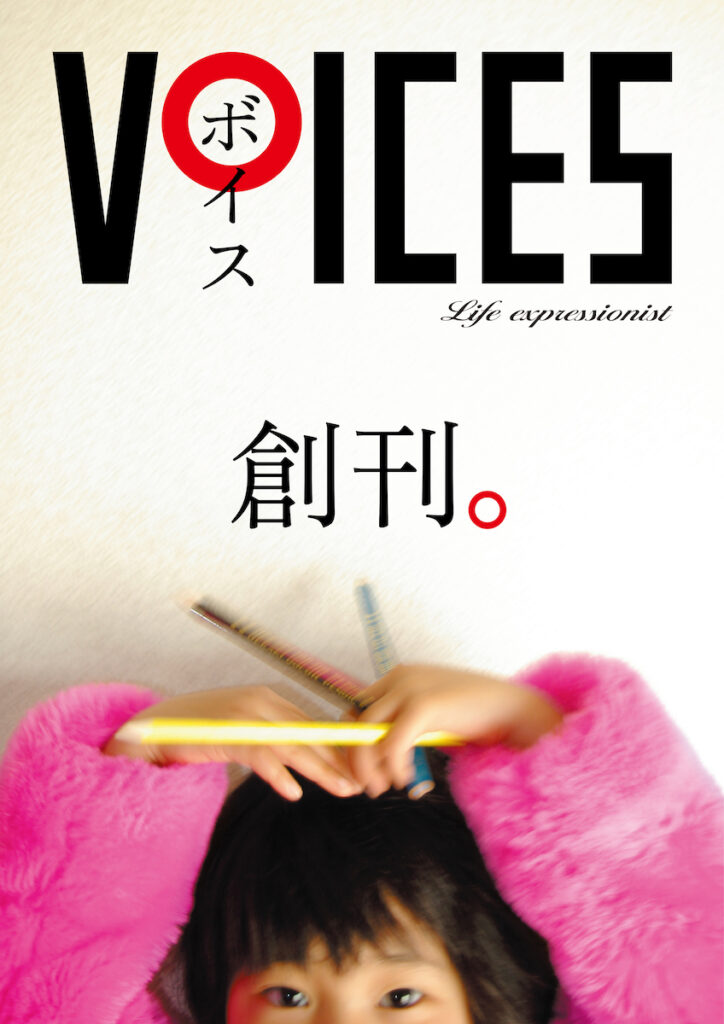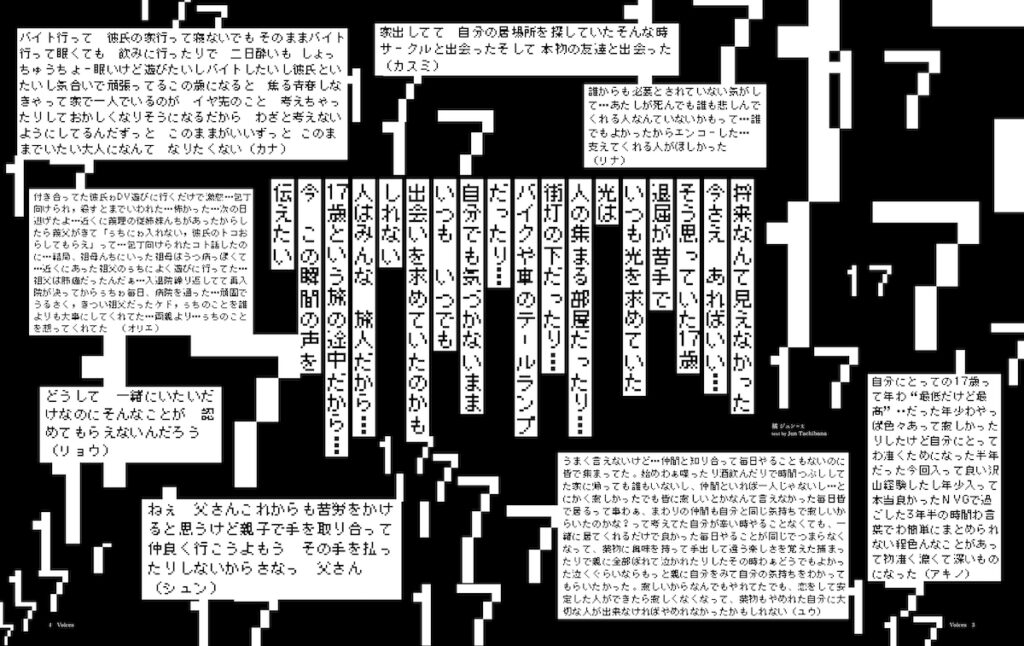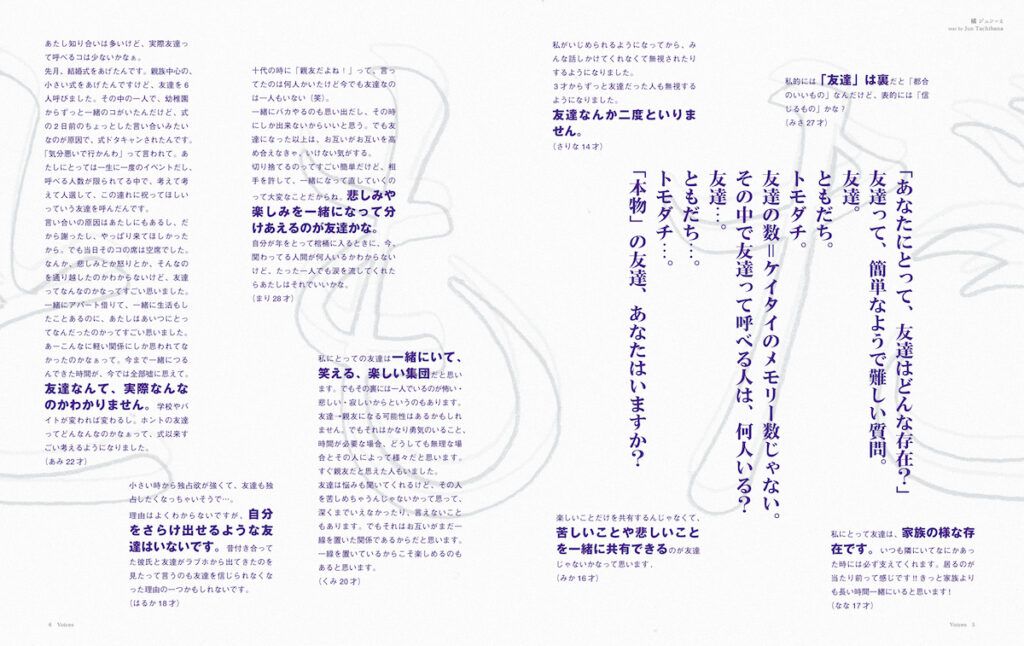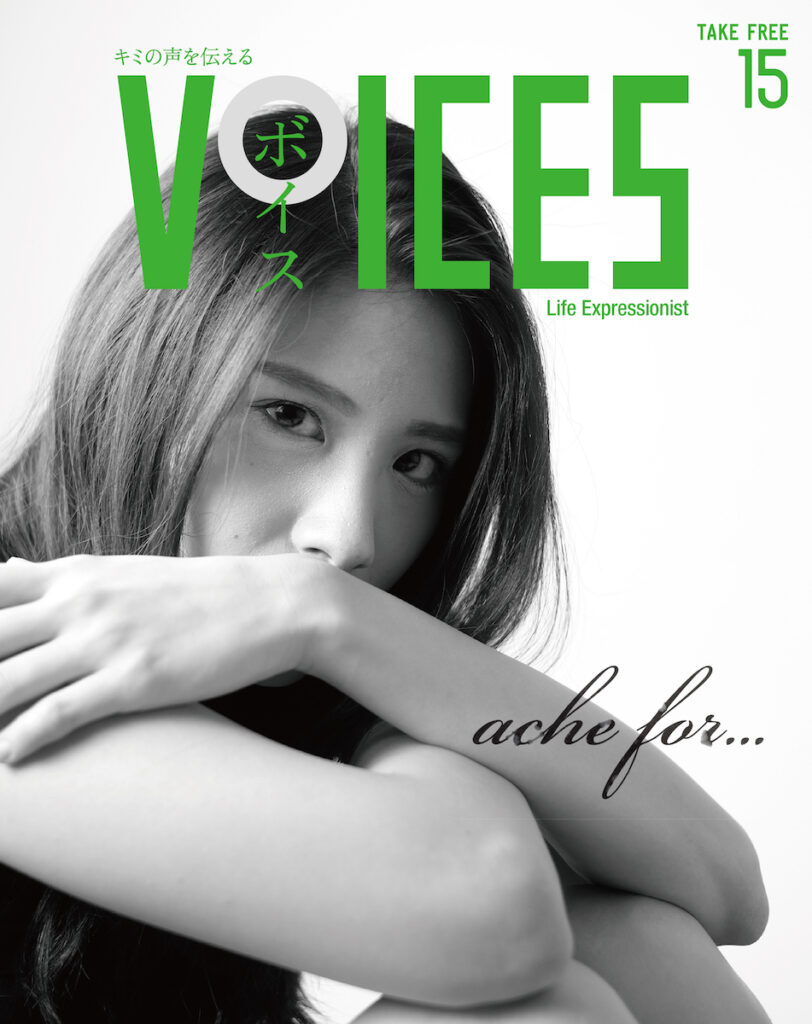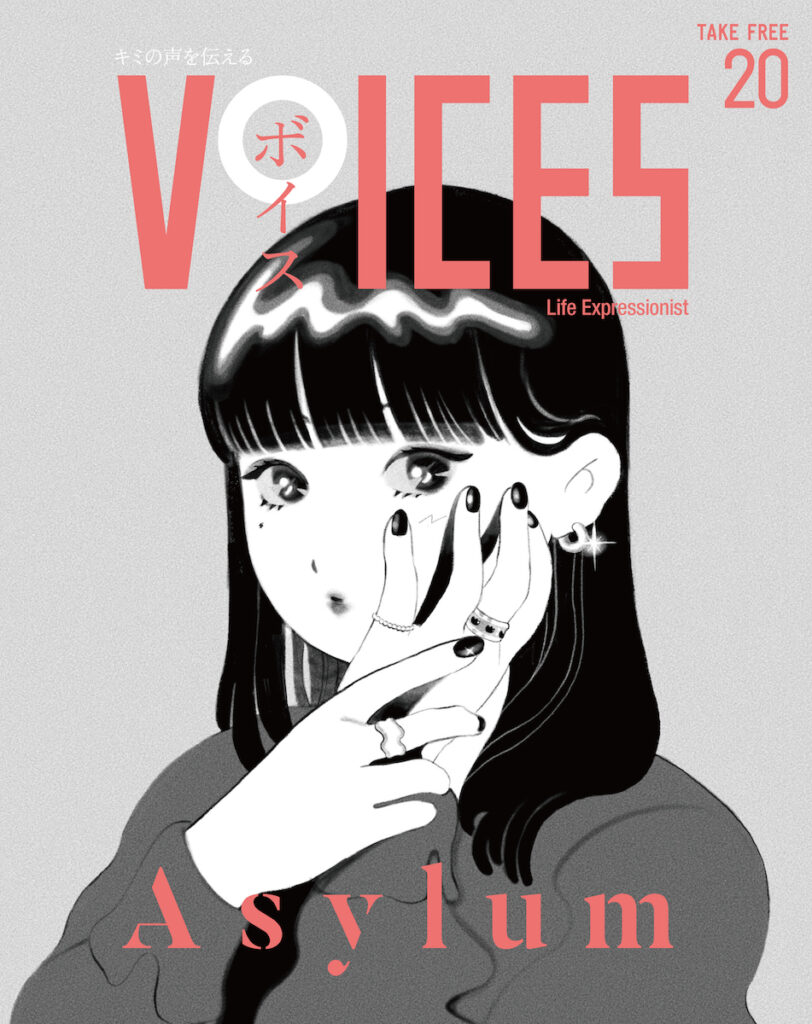“彼女は温かな優しさを求めているはずなのに、
向けられるのは偽りの優しさだった。”
2024.11/1 亜吏=文 / text by Ari 橘ジュン=校正 / Content Editor by Jun Tachibana
KEN=写真 /photography by KEN
※写真はイメージです。本文の内容とは関係ありません。 photo is an image. They are not related to the content of the text.
初めて会ったのは、
bondが運営している昼間の居場所でのことだった。
そこでは日中、女の子が過ごす居場所として対面でお話を聞かせてもらっている。
彼女は戸惑いながらゆっくりと扉を開け、
こちらが声をかけるまで入り口で佇んでいた。
花柄のワンピースを着た小柄な女の子。
彼女の名前を呼ぶと小さく頷いていた。
年相応ではあったものの、顔色が悪く、普段ご飯を食べられているか心配になるくらい細かった。
彼女は話したいと訴えてくれて、2人で話す機会を作った。
「今日はどんなことを話したくてきてくれたの?」
と私が問いかけると、
「全部疲れちゃった。」と、
小さな声で答えてくれた。
話そうという勇気を出してくれたものの、自分のことを伝えるのが難しかったのか、それ以降はこちらの問いかけに頷くだけになってしまった。
彼女がどんな気持ちを抱えているのか、
どんな思いを話に来てくれたのか。
初めて話そうとしてくれた彼女はとても緊張しているように見えた。
自分から話してもらうのは難しいのではないかと感じ、過去の相談を参考にして、家庭環境のことを質問してみることにした。
彼女は幼い頃から両親の暴力を受け、家に居場所がない。
父親も母親も彼女の味方ではなかった。
「お前なんかさっさと死んで。
お前がいること自体が迷惑。
価値もないのに。まだ生きてたんだ。
誰もお前が死んでも悲しむ人いないから。」
彼女は両親からそう告げられ、いつしか自分自身でも価値のない人間だと、生きている価値がないと思い込んでしまったのだ。
「私いるの迷惑だから早く死ななきゃ、消えなきゃ」
彼女はそう思わざるを得なかった。
彼女は温かいお風呂に入ることも許されなかった。
お湯を使うことを禁止され、家に誰もいない時間に帰宅して水でお風呂を済ませる。
使っていないように見せるために水滴の掃除をするのが大変だと教えてくれた。
「最近は氷水をたくさん作ってそれをかけられたり、お湯を氷水と交互にかけられたりする。ドライヤーで叩かれることもある」
ゆっくりと、そして苦し紛れに言葉を紡いでくれた。
更には家の家電を使うのが禁止され、
電子レンジや冷蔵庫、洗濯機の使い方も知らない。
「使い方を覚えてみたい」と、呟いた彼女の一言には、死にたいという気持ちとは裏腹に、生きることを諦めていない一筋の希望を感じた。
レンジでも、冷蔵庫でも、洗濯機でも、
使い方ならいくらでも教えてあげるから、
どうにか生きてほしい。私はそう思った。
家に帰るのが辛かった彼女は、
家では味わうことのできなかった温もりを求めて、外の世界へ居場所を求めるしかなかった。
彼女が居場所を求めた先には欲しかった温もりはなく、
悪意のある大人たちの汚れた欲望だけだった。
「1人は寂しいから、男の人について行っちゃう。探しちゃう」
彼女は公園や街中で男性から声をかけられるのを待っていると言う。
自分から声をかけることもある。
私は「ついて行く」「探す」ではなく、
「ついて行っちゃう」「探しちゃう」と、
悪いことをしているような口ぶりが気になった。
もしかしたら辞めたい気持ちもあるんじゃないかと思い質問すると「やめておけばよかったと思うこともある。でも、男性以外の寂しさの紛らわせ方が分からない」と、教えてくれた。